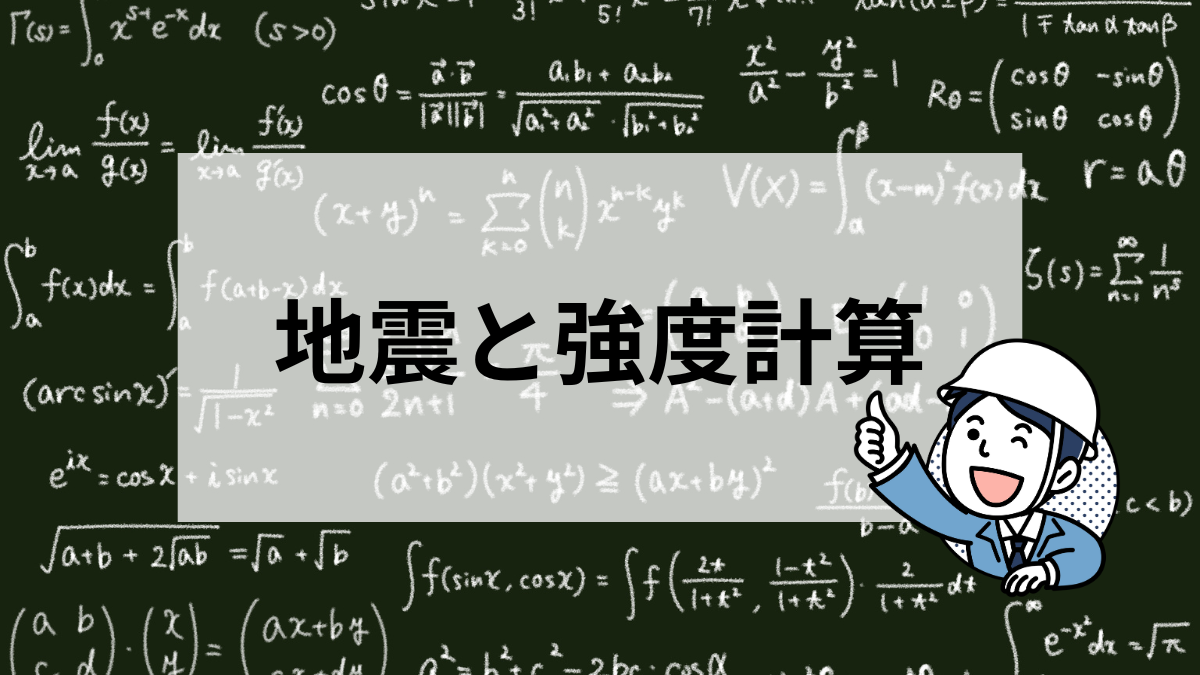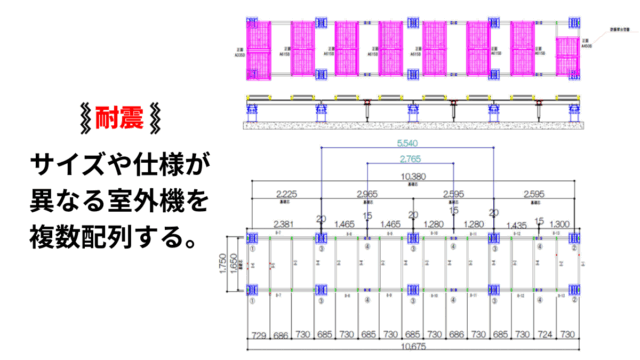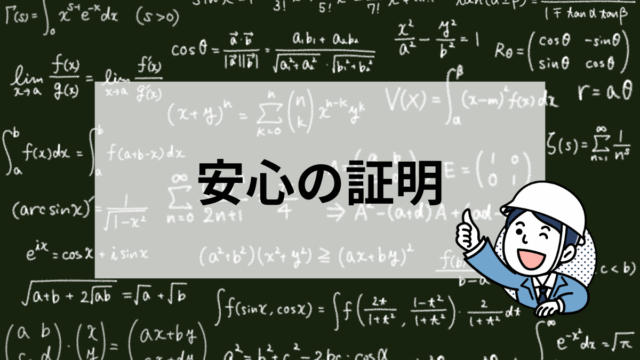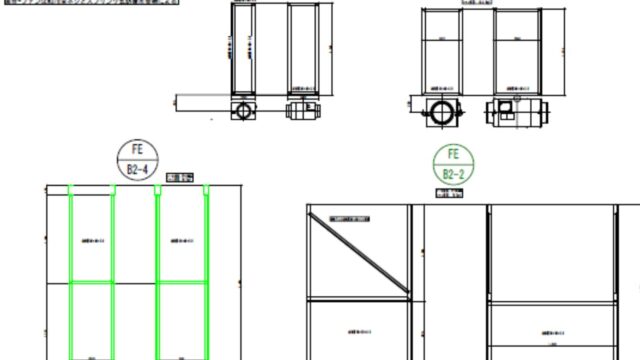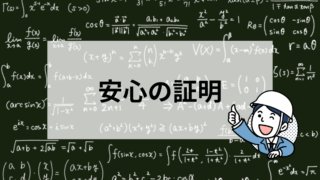図面と目的、必要な数値だけご提供いただければ、後は丸投げで強度計算を対応しております。
SMT Supportでは、耐震強度の計算も行っております。
今回は、今後も重要になっていく
「耐震に関わる強度検討」
について、簡易な記事を残しておきます。
興味のある方は、読んでやってください。
地震雷火事親父
古来より、地震はおそろしいものの筆頭でした。
今日でも、地震の脅威について説明は不要です。
今回は、地震について
耐震の視点から、数学的に捉えていきます。
あまり物々しくなりすぎないよう
(被災経験のある方に少なくないと思いますし……)
施工と耐震は切り離せない要素ですので、
強度検討の専門家として控えめの警鐘を鳴らします。
地震の強さは『いろいろ』
地震の強さは、「震度」や「マグニチュード」
といった尺度が一般的かもしれません。
こと、耐震の目線で行けば、
その物に与える地震力を 『Qi』で表します。
厳密に言えば、この数値は、
地上における『地震層せん断力』です。
地下では、計算が異なってきます。
Qi = ΣWi × (Zr × Rt × Ai × C0)
これが、地上におけるいち建物などへの
地震の影響力を数値化した式になります。
この数値に耐えうるか?
が、防震判定の可否になります。
また、建物や構造物全体ではなく、
設置物などの設備部分のみの場合は、
趣旨が少し異なり、計算式が違います。
KH (水平震度)= Kg × K1 × K2 × Z × Dss × Is×Ik
どの部分の防震か?
球として、面として、点として
地震の捉え方により、算出内容が異なるのです。
※私共の扱う地震の力は『点』にかかる負荷になります。
計算の要素
気象庁が扱う『震度』のように
設計関連では、基準震度というのがあります。
大地震≒基準震度0.4相当≒震度6相当 です。
地上から、基礎から離れるほど、上に行くほど、横に揺れます。
その揺れによる負荷の数値。
計測する『点』の重量次第で
必要な耐久数値が変わります。
統計的な地震頻度や大きさなどを加味したもの。
参照:地域別地震係数(国土交通省告示1793号)
風や積雪、『点』の重要性(病院など)、
経年劣化による耐性の低下などなど、
考慮しなければならないものはたくさん。
どの地域の、どんな対象物で、
どのくらいの地震に、耐える必要があるのか?
いろいろと加味して、計算を行います。
強度計算から思う防災意識
静止状態と比較して、時に何千倍と負荷がかかる。
それが、災害です。
事前の対策なく、その場の対応で、
どうこうできるものではないと考えます。
特に周囲に影響を与える『安全の保証』は、
『正しい情報』のもと『備え』なければ、
感覚だけに任せることはできません。
感覚では分かっていても、
数値で根拠を示すのは難しい。
そんな時の私たちです。
「たぶん、大丈夫」を確認しませんか?
強度計算書は、
構造物などの安全性を数値で証明するものです。
「これ、大丈夫かな?」
その確認、お任せください。
目的と計算に必要な数値さえあれば、
強度検討はできます。
ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・ご相談はコチラから